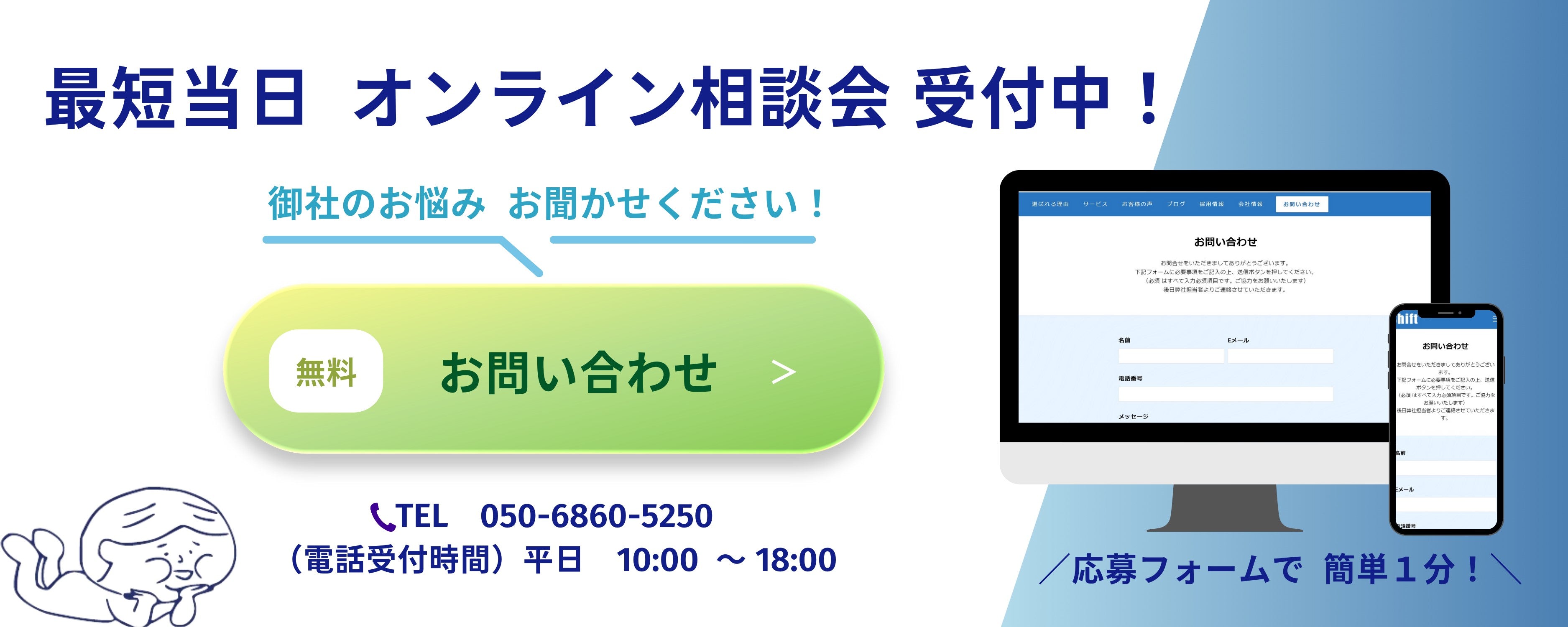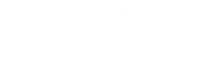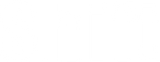【Indeed】採用活動において知っておくべき3つの重要指標

採用に携わられている皆さん、「応募が増えた」「クリック単価が下がった」=『採用がうまくいっている』と判断していませんか?
実際には、応募が増えても採用に結びつかなかったり、採用できてもすぐ離職してしまったりと、管理画面上の数字だけでは見えない課題が多く存在します。
本記事では、採用活動を行う上で無視できない3つの重要指標——
応募単価・採用単価・定着率について、実際の運用視点から解説します。
①応募単価相場
応募単価は「広告の効率」を表す、最も分かりやすい指標のひとつです。
応募単価を構成する要素は、勤務地・給与・待遇・仕事内容・応募資格など、さまざま。
競合環境やターゲットの希少性によって応募単価は大きく変動します。
たとえば、地方の介護職と都市部の営業職では、クリック単価も応募率もまったく異なります。つまり、応募単価の良し悪しを語るには、まず「相場」を知ることが前提条件です。
この“市場を基準にした評価軸”を持つことで、
「自社の成果が本当に悪いのか、それとも市場並みなのか」を正確に判断できるようになります。
採用相場を知っていれば、自社の待遇面を見直しなども効率よく実施することが可能です。
応募単価の相場を知る2つの方法
① Indeedのレポートや競合掲載の傾向を確認する
同じ職種・エリアでどんな企業がどのような条件で訴求しているのかを把握することで、
自社のポジション(=市場内での立ち位置)が見えてきます。
そのうえで活用したいのが、Indeedの「採用市場レポート」です。

このレポートでは、職種別・地域別・時期別に「求職者数」「求人数」「平均給与」などのデータが集約されており、
今どのエリア・職種で採用競争が激しくなっているかを、客観的なデータで可視化できます。
また、季節や時期による変動傾向も確認可能です。
たとえば、3月・9月は転職活動が活発化し応募単価が下がりやすい一方、
お盆や年末年始などは応募が減少し、単価が高騰するケースが多く見られます。
このように「時期的要素」も相場を読むうえで欠かせない観点です。
②運用代理店から情報収集をする。
最近では、Indeedをはじめとした求人媒体の営業電話が多くかかってきますよね。
「今この職種が狙い目です」「このエリアは単価が上がっています」など、
営業担当者は日々多数の案件を扱っているため、最新の市場感を持っています。
もちろん、すべてを鵜呑みにする必要はありません。
複数の代理店・媒体担当者の話を比較しながら、
「どの数字に一貫性があるか」「どの情報が現場実感と一致するか」を見極めることが重要です。
特に、定期的に取引のある代理店がある場合は、
エリア別・職種別の平均応募単価データを共有してもらうようお願いしてみましょう。
最新トレンドや成功事例を交えた情報をもとに判断することで、
“自社の応募単価が市場と比べてどうか”をより正確に把握できます。
②採用単価
応募単価が低い=効率が良い。
一見するとそう思われがちですが、実際の採用現場では「応募の質」や「採用率」を無視した判断は危険です。
応募単価が低くても、面接辞退やマッチングミスが多ければ、
結果的に採用までに必要なコスト(採用単価)は上昇します。
逆に、応募単価がやや高くても、的確なターゲットに届き、採用までの歩留まりが良ければ、最終的なコスト効率は高くなります。
私たち運用者が追うべき本質的な指標は、
「応募数」ではなく“採用1件を得るまでのコスト構造”です。
採用単価に注目する 〜本当の“効率”を見極める〜
採用単価(Cost per Hire:CPH)は、以下のように算出されます。
採用にかかった総コスト ÷ 採用人数
ここでいう「総コスト」には、媒体費や運用手数料だけでなく、
面接や連絡対応にかかる人的コスト、採用管理ツールなどの間接コストも含まれます。
つまり、応募単価よりも“現実の採用効率”を反映した指標が採用単価です。
応募単価はあくまで入口の効率を示す指標であり、
そこから面接設定率・面接実施率・内定承諾率といった“歩留まり”が積み重なって初めて採用単価が形成されます。
例えば以下の2つのケースを比較してみましょう。
| ケース | 応募単価 | 面接実施率 | 採用率 | 採用単価 |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,000円 | 50% | 10% | 約40,000円 |
| B | 3,000円 | 80% | 20% | 約18,750円 |
Aは応募単価が安いにもかかわらず、歩留まりの悪さによって結果的にコストが高騰。
一方でBは応募単価が高くても、面接率・採用率が高いため総合的な効率は優秀です。
このように、「安い応募を集める運用」ではなく、「採用につながる応募を生み出す運用」が本質的な成果を左右します。
採用単価を改善する2つのアプローチ
① 応募後の体験を最適化する
応募後のレスポンス速度や面接日程調整の手間が歩留まりに大きく影響します。
システム連携や即時返信の自動化など、応募後フローのUX改善が採用単価改善の第一歩です。
② 求職者のマッチ度を高める原稿設計
「応募は多いが不一致が多い」場合は、原稿内容に原因があります。
仕事内容・求める人物像・条件面を具体的に明記し、時には“ターゲットを絞り込む勇気”を持つことが結果的に効率改善につながります。
③定着率
採用単価を下げ、効率的に人材を採用できても、
入社後すぐに離職してしまえば意味がありません。
真の採用成果とは「採用できたか」ではなく、「定着し、活躍しているか」で判断すべきです。
近年、採用市場では“早期離職”が増加傾向にあります。
背景には、ミスマッチによるギャップ・期待値のずれ・オンボーディング不足などがあり、
どれだけ広告運用を最適化しても、入社後の環境が整っていなければ効果は持続しません。
Indeedや各種媒体で得られるデータは、あくまで入口の情報です。
応募単価 → 採用単価 → 定着率と視点を拡張することで、
「採用の効率」から「人材の成功」へという本質的な改善サイクルを描けます。
まとめ
クリック率(CTR)や応募・採用単価など、様々な指標がありますが、
指標は単独で評価するものではなく、相互の関係性を読み解くことで初めて価値が生まれるのです。
応募単価を分析し、採用単価で成果を測り、
最終的には“定着・活躍”という長期的な成功にまで視点を広げる。
その全体像を意識して数字を見ていくことで、採用活動を成功へ導けると考えています。